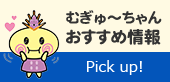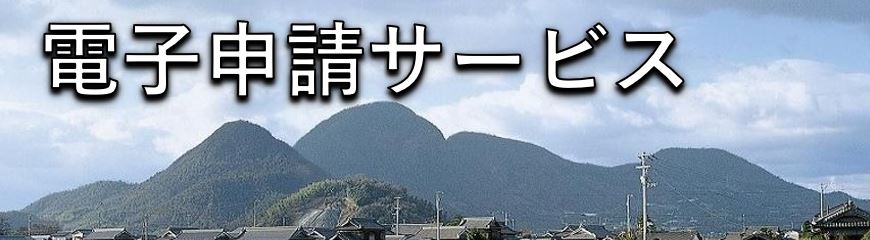本文
善通寺市デジタルミュージアム 磨臼山古墳 割竹形石棺
国指定重要文化財 割竹形石棺~善通寺市生野町磨臼山古墳出土~
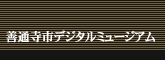

石棺とは、古墳に埋葬するために有力者の遺体を納めた「石のひつぎ」のことで、身と蓋で一対となり、断面が円形のものを「割竹形石棺」と呼びます。この石棺は、昭和31年に史跡有岡古墳群の磨臼山古墳(前方後円墳)から出土したもので、古墳時代前期(4世紀後半)に造られたものと考えられています。
石棺の内部には朱が塗られた痕跡があり、被葬者の頭を置く位置には石枕が勾玉の装飾とともに浮彫りされているなど、全体的に精美な加工が施されています。
石材は高松市国分寺町の「鷲ノ山(わしのやま)」から産出する角閃石安山岩「鷲ノ山石」が用いられており、鷲ノ山石でできた石棺は県内の有力な首長の古墳の他、海を越え大阪府柏原市の古墳まで運ばれています。石棺は被葬者を安置する重要なものであるため、石棺に同じ石材を利用した地域には、政治的な結びつきがあったのかも知れません。
この石棺は残りが良く、当時の石工技術の高さをうかがい知ることができるため、国の重要文化財に指定されています



所在地
ZENキューブ1階 善通寺市立郷土館石棺保管展示室(文京町2丁目1-4 )
JR善通寺駅から歩いて約3分。