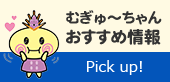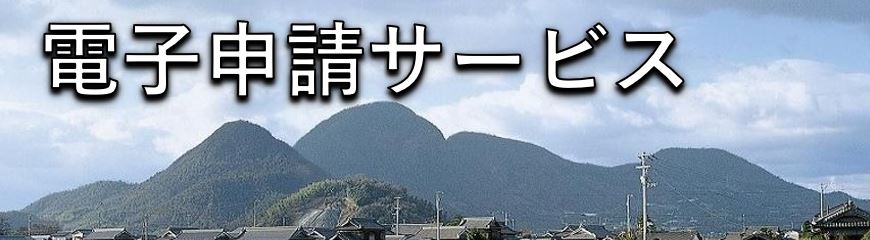本文
43)善通寺の獅子舞(六条獅子組)
43)獅子舞(六条獅子組)
獅子舞の内容
牡丹くずしと言われています。また口上があるということです。(香川県の民俗芸能-平成八・九年度 香川県民俗芸能緊急調査報告書- 平成十年三月瀬戸内海歴史民俗資料館の調査より)
歴史
昭和8年の奴組の写真が残されていますが、この頃には既に獅子組もあったと聞いています。確認できるものでは昭和22年の集合写真が残っています

獅子舞に用いる道具・構成等
平成8,9年 塗獅子。成長する若獅子の姿。太鼓、鉦、幟旗、高張提灯。天狗、太鼓打ち。(香川県の民俗芸能-平成八・九年度 香川県民俗芸能緊急調査報告書- 平成十年三月瀬戸内海歴史民俗資料館の調査より)
平成26年取材時には、獅子1頭、和太鼓2つ、平太鼓3つ、鉦3つの構成でした。また、幟も確認しています。なお、この地区には笛が今なお伝わっております。
令和6度アンケート調査時の道具は太鼓 2台、 鉦(かね)4台、平太鼓(半太鼓)4台、幟(のぼり) 1台 獅子 1頭、 その他(笛など)笛4本とのことでした。
この地域にのこる口上
これ獅子の由来は在昔印度支那のことなり、中古わが国に伝来獅子の形態をつくり、これ祭祀用い、この舞曲を奏し、神明を慰め奉る
そもそも獅子の物たる獣中の王にして、百獣ひとたびこれに遭うときは、たちまち生気を失い幽谷に逃匿す。
しかりといえども、獅子の懍性たる大を抑え、小を救い悪をこらしとめ善を助くる。故にこれを祭祀に用いるときは神明を慰め奉り、これを人に用いるときはもろもろの災禍を除き、天下泰平、国家安全、五穀豊穣の基となるべし。
千秋万歳 敬白
動画
六条獅子組の動画です。
こちらの獅子組は鉦が3つあり、鉦の質・大きさにより、微妙な音色のずれがあるため、独特の響きを生み出します。(動画では高めの音が聞きづらくなっていますが、実際の音は三重の音のずれが絶妙です。)
また、笛の演奏もあり、よその獅子組とは一味ちがった音色を聴くことができます。ぜひご覧ください。
写真
今回は新羅神社(金蔵寺)の六条獅子組です。
村づかいの様子です。
六条獅子組のマストアイテム・・・「カート」です。楽しそうです。
ここからは昨年の写真です。
村づかいの風景です。
六条獅子組は、和太鼓2つと平太鼓2つ、鐘3つの構成です。油単は黒地で、金の雷紋(もしくは菊でしょうか)がデザインされています。
この獅子組は作法がしっかりしている印象があります。
まず、各家で舞う前に、舞い手が家に向かい手を合わせ、礼をしてから舞います。
そして、子どもたちは太鼓の演奏が終わるとこのようなかたちでかしこまり、礼をしてから終わります。
六条獅子組は、獅子舞を通して、礼儀もしっかりと教えている気がしました。
また、この獅子組は獅子舞に笛の伴奏があります。笛は、市内でも数えるほどしか残っていません。
撮影に協力いただき、ありがとうございました。