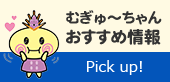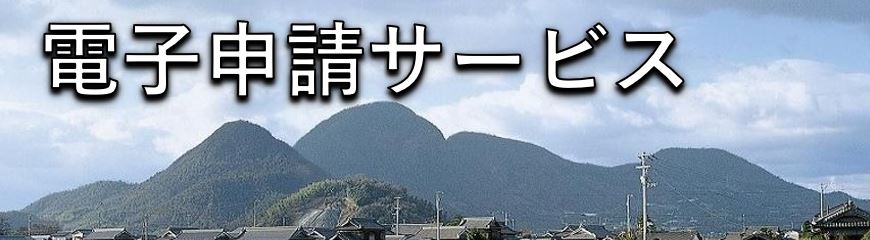本文
固定資産税と都市計画税の課税のしくみ
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を、その所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画税とは、道路、公園、下水道などの「都市計画施設」の整備に関する事業や市街地開発事業、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただく目的税です。
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)
| 土 地 | 毎年1月1日現在、土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 屋 | 毎年1月1日現在、建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 | ||||||
| 償却資産 | 毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(都市計画税はかかりません。) | ||||||
※償却資産とは・・・
会社(法人)や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などをいいます。
固定資産税・都市計画税の税率
課税標準額×税率で税額を算出します。
固定資産税 1.4%
都市計画税 0.1%
固定資産税・都市計画税のかからない人(免税点)
同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産について、それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税、都市計画税のいずれもかかりません。(ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。)
| 区 分 | 免 税 点 | ||
|---|---|---|---|
| 土 地 | 30万円 | ||
| 家 屋 | 20万円 | ||
| 償却資産 | 150万円 |
土地について
【評価のしくみ】
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
1 地目
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)現在のその土地の現況及び利用目的に重点を置き認定します。
2 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。善通寺市の場合、平成25年度までは地籍調査が完了している地域と完了していない地域の均衡を図るため、一部地籍調査前の登記地籍に据え置いて課税してきました。しかし、地籍調査による登記が、平成25年中に市内全域で完了したため、平成26年度から原則どおり、登記地籍での課税をおこないます。
3 価格(評価額)
土地の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格から不正常な原因を除いた正常売買価格を求め、それを基礎として算出されたものです。
【住宅用地に対する課税標準の特例】
住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
1 住宅用地には、以下の2種類があります。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)が、住宅用地になります。
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が、住宅用地になります。
2 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)現在において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存のこの家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
3 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ | 専用住宅 | 全 部 | 1.0 | ||||
| ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | ||||
| 2分の1以上 | 1.0 | ||||||
| ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | ||||
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||||||
| 4分の3以上 | 1.0 | ||||||
4 住宅用地に対する課税標準の特例
(1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税の場合は3分の1の額)とする特別措置があります。
(2)一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税の場合は3分の2の額)とする特例措置があります。
注:よく、「家を取り壊したのに固定資産税が上がった」というお問合せがありますが、これは、住宅を取り壊したことによって、土地に対する上記の特例措置が適用されなくなったことによるものです。特例措置が適用されなくなることで、税額が大幅に上昇することもあります。
家屋について
【評価のしくみ】
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
1 新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
※再建築価格
・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※経年減点補正率
・・・・・建築後の年数の経過によって一般的に生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
2 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格(※)は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、算出された評価額が前年度の価額を超える場合は、原則として前年度の価額に据え置かれます。
(※)在来家屋分の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格 = 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
【新築住宅に対する減額措置】
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
1 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
(1) 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
(2) 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
2 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
3 減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
4 減額される期間
(1) 一般の住宅(木造住宅など)・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅(マンションなど)・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
【家屋に関する各種届出について】
1 未登記家屋所有者変更届
売買等により、登記していない家屋(未登記家屋)の所有者に変更があった場合、届出が必要です。
未登記家屋所有者変更届の様式 [Wordファイル/44KB]
2 家屋滅失届
家屋を取り壊した場合、届出が必要です。
(注)いずれの様式もダウンロード後、必要事項を記入し、個人印または社印及び代表者印を
押印し、提出(郵送または持参)してください。