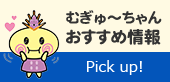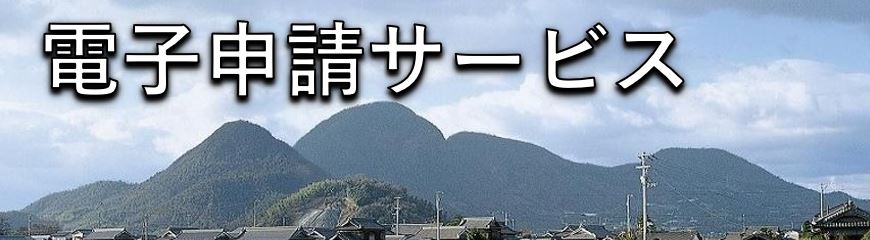本文
南海トラフ地震とは?
南海トラフ地震とは?!
南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として過去に大きな被害をもたらしてきた大規模地震です。過去の事例を見てみると、これまで100~150年の周期で大規模な地震が発生しており、1707年の宝永地震のように駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生したり、マグニチュード8クラスの大規模地震が隣接する領域で時間差をおいて発生したりするなど、その発生過程に多様性があることがわかります。地震調査研究推進本部の長期評価によると、マグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は70~80%(令和6年4月1日現在)とされています。
このような中、南海トラフ沿いの地域では、東北地方太平洋沖地震を教訓に、最大クラスの巨大な地震・津波を想定し、突発的な地震発生に備えた事前対策から事後対応、復旧・復興まで、地震対策の取組が総合的に進められています。
国の被害想定では、津波による死者が最大で22万4千人と甚大な被害が想定されているところですが、地震直後に避難を開始する住民の割合が高くなり、さらに津波情報の伝達や避難の呼びかけがより効果的に行われた場合には、想定に比べて約8割の被害軽減効果が推計されています。
一人一人が迅速かつ主体的に避難行動が取れるよう日頃から備えましょう。
※詳しくは気象庁のHPを確認してください。https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/index.html
南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件
「南海トラフ地震に関連する情報」は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするもので、この情報の種類と発表条件は以下のとおりです。
|
情報名 |
情報発表条件 |
|---|---|
|
南海トラフ地震臨時情報 (注1) |
・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 ・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 |
|
南海トラフ地震関連解説情報 (注2) |
・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合 |
(注1)「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施できるよう防災対応等を示すキーワード(「調査中」、「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」)が情報に付記されます。
(注2)すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります。
(注3)「南海トラフ地震臨時情報」(「調査中」、「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」)が出される具体的な場合については、下記気象庁のページをご参照ください。
南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件(気象庁HP)https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/info_criterion.html
南海トラフ地震(最大クラス)が良くわかる動画の紹介
香川県では南海トラフ地震が発生したときに備えて想定される被害の状況等を動画にしています。もし、大規模地震が発生したときに自分や自分の家族を守るためにどのような避難行動をとるのかについて、参考にしてみてください。